人種や性別、生まれに関係なく能力の高いものが成功できる「平等な」世界。そんな世界を理想とし、追い求めてきたにも関わらず、現在では格差が拡大し新しい階級社会が作り上げられている。本当に能力主義は正義なのか、真に正義にもとる社会へと変えていくことは可能なのか。ハーバード大のマイケル・サンデル教授が現代の難問に挑む著作。
アメリカの格差の現状
大学入試
能力主義の象徴的な存在である高等教育。真の意味で機会が平等に与えられているのならば、大学の学生の構成割合は、所得とは関係ないはずである。そう信じたい。しかし、現実は違った。アイビーリーグの学生の3分の2あまりが、所得規模で上位20%の家庭の出身なのだ。逆に下位20%にあたる家庭の出身者は4%にも満たない。アメリカの大学に入るには、学業成績も重要だが、ボランティア活動やスポーツの成績も大事な要素となる。言い換えれば、名門大学に入るために幼い頃からさまざまな経験を積ませられる余裕のある家庭の方が有利な状態だとも言える。入試コンサルタントなぞ付けた日には、所得との関係を認めるしかないだろう。科目試験一発勝負の日本の入試制度の方がまだマシに思える。
アメリカンドリーム
アメリカ人の経済状態ではどうだろう。アメリカの社会的流動性(次の世代が異なる階級へ移動すること)を見ると、所得規模で下位5分の1に生まれた人のうちで上位5分の1まで達するのは20人にひとりの割合だ。しかも大半の人は、中流階級にさえ到達できない。これは、ドイツやデンマークなどのヨーロッパ諸国などよりも低い数字だ。貧困からのしあがる代名詞であったアメリカンドリームは、もはやアメリカに存在しない。社会的、経済的に成功したかったら他の国に行ったほうがいいのだ。
では、何が問題なのか。どうすればいいのか。
現状はわかった。では、何が問題なのか。そのひとつは、成功をおさめた人々が往々にして、その成果は自分の努力によるものだと信じていることなのだ。逆に言えば、上手くいかなかった人達は、能力や努力が足りなかったためだと考えているのだ。一見すればまともなようだが、過度な能力主義が他者への思いやりや想像力を阻害している裏返しだと言える。自分が、いい大学に入れたのは高等教育への理解があり経済的協力を惜しまない両親の元に生まれたことは関係ないと言えるだろうか。世の中には学問に否定的で、子が勉強することに協力的でない親が存在する。はたしてそこに開かれた門戸は「平等」と言えるだろうか。ひとつの答えは、「謙虚であること」だ。過度な能力主義は、自身の運命の全てが手の中にあると錯覚し、異なる階層や価値観の人々との連帯を損なう。もし、出自や環境が違っていたら自分が手にする結果も違うものだったと思える人が増えることが、寛容な社会を作るのだ。
勝手に考えたこと。
アメリカがいかに能力主義に傾いているか、分断を生んでいるかという事実を交えた文章は、意外な真実といった感じで面白く読めた。結論が少々弱いとも感じた(そもそも謙虚になったところで格差が是正されるわけでわない)が、ここまで歪んでしまった社会を一発で治してしまうような言説の方がさらに疑わしいので、ひとつの落とし所だったのだろう。
ふと、舞台を日本にして考えてみる。日本でも似たようなものだ。学歴偏重主義で子供の貧困が叫ばれている。アベノミクスと言いながら、実体経済は全然進歩していない。富めるものはさらに豊かに、貧しいものは抜け出すことができない。硬直化した階級の中で価値観は分断され、対立は深まるばかり。『証券マンとコンビニ店員どっちが上?』と聞かれたら、大半の人が証券マンと答えるだろう。何をもって『上』としたのだろうか。お金?お金はわかりやすい尺度だ。簡単に比べられる。では、給料は本当にその仕事の価値に対するものなのだと言えるのか。この質問に食い気味に「はい!」と答えるのが、能力主義だと僕は思う。でも、みんなコロナで気づき始めたかもしれない。医療従事者やゴミ清掃員、小売店の従業員がいなければ成り立たない社会の上に生きていることを。ここが「謙虚さ」と「リスペクト」のある社会への始まりだと信じたい。
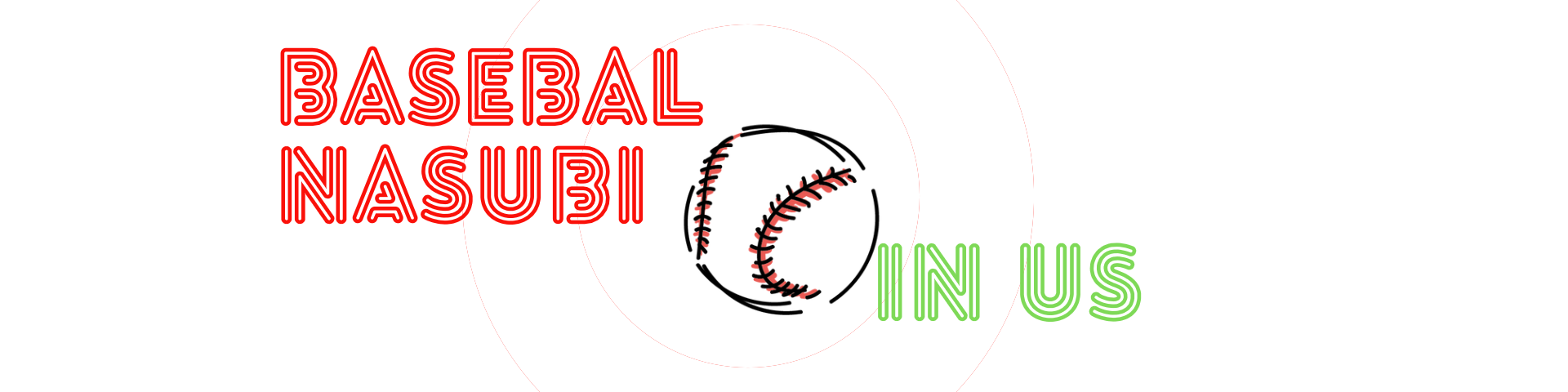



コメント